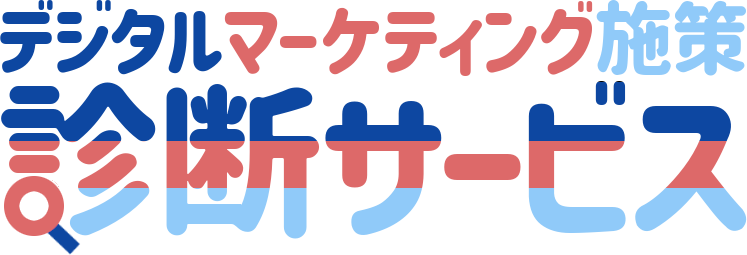マーケティングの今とこれからを探っていく連載コラム「ボーン・トゥ・プラン ~明日なき計画~」。第15回目の今回は情報が簡単に手に入ることで変化した人々の心理変化や多様性への影響を考察します。更には生成AIなどをどう扱うか、情報処理するスキルが逆に求められている時代なのでは、、そんな今とこれからをアナイグマとともに探っていきたいと思います。
第14回はこちら。
- 目次
- アナイグマって??
- イントロダクション
- 情報が得られる=当たり前?
- 情報過多の弊害
- 多様性という概念
- マーケティングにとっては
- 結局自分たちで理解することが大事
- 生成AIも「使われてるだけ」ではダメ
- HAKURAKUって生成AI使ってますよね?
- アナイグマのひとこと
アナイグマって??
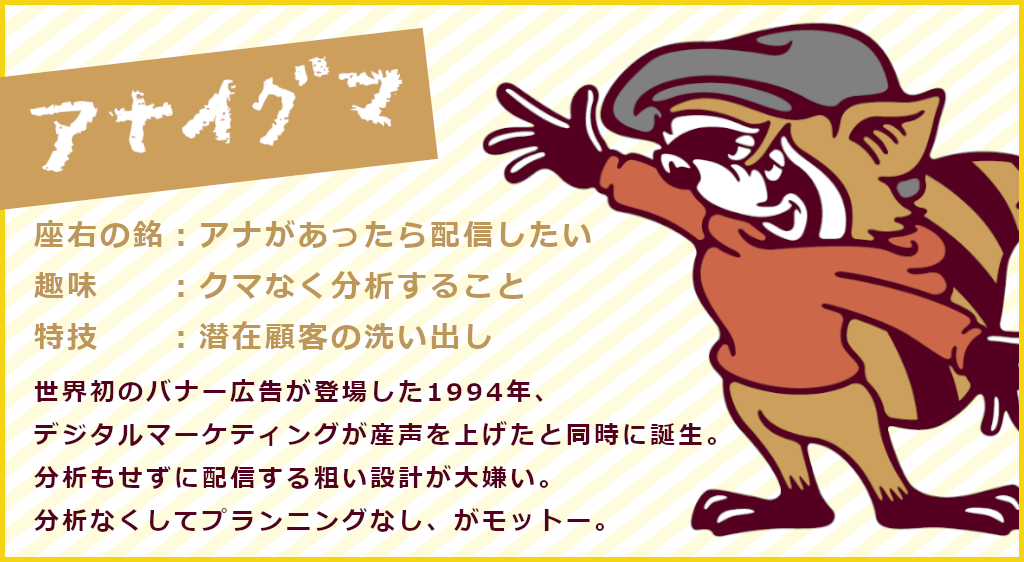
イントロダクション

うーん、どういうことなんやろ、、
どうしたの?珍しく悩んでるじゃん

珍しくって、僕だって真面目に悩むことありますよ!甥っ子にプレゼント考えてて、なんか最近写真撮るのが好きみたいなので、キッズカメラを探してるんですけど、、
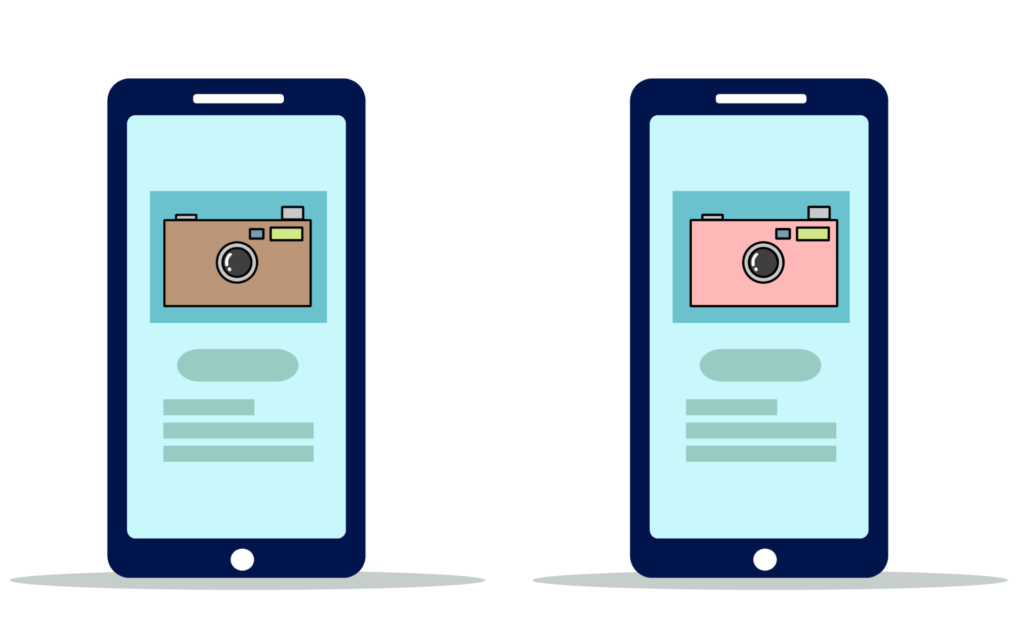

これって同じ形なんですけどメーカーも違うし、なんか機能も微妙にちゃうんですよね。
ほんとだ。どこか同じところで作ってるOEMの商品なんじゃない?

確かに!そうかもしれないですね。でもどうして違うとこがあんねやろ、、
まぁ見た目一緒で微妙に機能差があると気になるよね。

そうなんですよ。これだけネットで調べてもわからないなんてことあるんですね。
…あぁそうか。君たちくらいのデジタルネイティブだとそう感じるわけね。

そりゃ何でもかんでもわかるとは流石に思ってないですけど、こんなんわかりそうなもんやないですか。
情報が得られる=当たり前?
情報が簡単に手に入る時代になってはや数十年。
インターネットの登場からSNSの台頭と、時代とともに得られる情報は増加し、発信側も所謂企業・専門家だけでなく、一般ユーザーが多くなっています。
そのため情報自体の信憑性が問われることも増えましたが、誰もが情報を取得できることが当然、という状態になっているのは確かです。
逆に言うと、「知れなくても気にならなかったこと」が気になってしまう時代になったよね。

昔は気にならなかったんですか?
気にならないも何も、わからないことが当たり前だったから、知りたい!という気持ちを抱く前に受け入れてたんじゃないかな。

そう考えると昔の人は損してますね。
損、、そうかもしれないね。でも知る必要のないことを知って、悩みが増えてるのは今のほうじゃない?
情報過多の弊害
前回(第14回)でも情報過多による昔との違いには少し触れましたが、多くなったことで選択肢が増え、決断の前の「比較・検討」フェーズが重くなり、ネットで簡単に買えるはずなのに、買う状態になるまで時間がかかる、というジレンマが生まれました。
更にユーザー発信(UGCなど)が増えたことで迷わされることは皆経験してるんじゃないかな。そもそも、ユーザー発信だから本当かわからないし、疑心暗鬼になるという精神衛生上も良くない世の中になったとも言える。

確かにまず疑うって感じですね。
デジタルが犯罪に使われるってことも関係していて、インターネット初期からある「ワン切り」詐欺とか、なりすましメールとか、何かしら届いたらまず疑う、が定着したよね。

世知辛いっすね、、
あとはフェイクニュースとか、陰謀論とか、何が正しくて何が嘘なのかがわかりにくくなったね。
多様性という概念
もちろん悪いことだけじゃなくて、今では共通認識になりつつある「多様性」を認めるっていうのも現代ならではかな。
情報が増えたことで世界が広がり、自分だけが悩んでいたのではなく、他にも同じ悩みを持つ仲間がいるということが多様性を認める社会に多大な影響を与えたのは言うまでもありません。
こうした仲間同士のコミュニティが従来以上に形成されやすく、拡大していき、細分化していく。

なんか便利な言葉やなっていう気もしますけどね。
そう、多様性っていう個性を尊重する「良い時代」になってきたとすると、どうしてもそれを利用するっていう輩が生まれるのは仕方ないからね。まぁ乱暴な言い方だけど、そういう奴らに嫌悪感を抱くのも、同調して受け入れるのも、多様な考え方なんじゃない?
マーケティングにとっては
マーケティングの世界でも多様性に対応した訴求、ターゲットの考え方などは普及していますが、果たして本当に対応できていると胸を張って言えるマーケターはどれくらいいるでしょうか?
多様という深い森に迷い込んで芯を見失ってる人も少なくないのでは?

僕のクライアントでも、ターゲットはこれくらいの年代、で今の時代に合わせて訴求はこんな感じ、みたいな設計はしてますね。
そうだよね。そして今のWeb広告の主流ってプラットフォームに任せる、っていうのがスタンダードじゃない?

まさに。GとかMとかは機械学習が優秀なんで、細かく設定するんじゃなくて拡張とかに任せてます。
それはそれで効果的なんだろうけど、なんでそうなったのかっていう過程とか理由がわからないよね。

そうですね。。ようわからんけどええ感じにしてくれるからええやん、っていう。
多様化しているユーザーだからプラットフォームの機械学習で多方向に寄せていくのは合理的です。ただ、多様化しているその内訳に理解が無いまま進んでいくので、結果得られる知見が少ない、っていうことに陥るのではないでしょうか。
結局自分たちで理解することが大事
マーケティングって理系的要素だけじゃなくて文系的要素も必要なんだよね。

突然どうしたんですか?
Web広告って基本的に数値で語るでしょ?CPAがいくらで、みたいなKPIを追って。

配信モノは特にそうですね。というかそれだけってクライアントも居ますね。
だからプラットフォームに任せるっていうのも実に理系的な確率の世界では当然だと思うのね。でもなぜそのコミュニティなのか、訴求がこれなのか、っていう数値だけでは測れない部分は絶対軽視しちゃいけない。だって次の新しいことに向かうヒントもわからなければ、手詰まったときどうするの?

(あつい、、)
機械で出てきたものは人間が判断するための材料に過ぎない、というスタンスを持ち続けることが重要なんだよね。
生成AIも「使われてるだけ」ではダメ
生成AIも同じことが起こりやすく、使ってるつもりが使われている、といったケースが増えています。AIが提案してきた内容をあたかも自分で考えたかのように錯覚し、生み出した気になってしまうのです。
これで何が起こるかというと、想像力・創造力が備わらないだけでなく、AIが生み出すものしか作れなくなっていくってこと。

でも今の時代、AI使わないっていうのは取り残されますよね?
もちろん。だからこそ使えるようになるというスキルと、錯覚を起こさないマインドを持つ必要があるんだ。

そんなに大袈裟なことじゃないんじゃ、、
今はそうかもね。でもAIがそれこそ当然になったら一瞬でそんな世界になると思うよ。逆に言うと、今から意識的に実行していくことが他の人との違い、つまり差別化になるんじゃないかな。基本的に人間は怠け者だから、生成AIのような革新的なモノが出てくるとどうしても依存という沼にハマりやすい。そこで自身の考えをミックスしてよりクオリティ高くユニークなものを生み出していくことが大事なんだ。
HAKURAKUって生成AI使ってますよね?
第12回でも触れた新しい分析ツール「HAKURAKU」。
SNSのデータを基にユーザーの興味関心を可視化する機能がありますが、その部分のキモとなるのが生成AIによるペルソナ作成。

HAKURAKUも生成AIで導くと思うんですけど、アナイグマさんの言うように実践するのはどうしたらええんですか?
まず、HAKURAKUでは投稿データを基にしてペルソナを推定しているんだ。その投稿データをどれにするか、つまり人間の目で膨らませたい投稿を選ぶ工程があるから、全部AIにお任せっていう単純なものじゃないんだよね。

それは恣意的って言われちゃうんじゃ、、
そうだね。そこのバランスが難しい。だから今追加で開発しているのが、AI×人間の掛け合わせ部分の強化なんだ。詳しくはまだ言えないけど、ある手法でAIに指示を出して投稿をまとめさせることで、選ぶ工程が単なる人間の独断だけでなく、AIの手助けと相乗することでいいとこどりをするんだよ。

なるほど、、ようわからんけど凄そうですね。
そりゃ簡単にわかるようなもの作っても仕方ないからね。

なんか凄そうですけど、作ったのってアナイグマさんじゃないですよね?
ん?

自分の手柄みたいに言うから、、
そ、それは開発にも私の手助けがあったからこそ掛け合わせになって、、
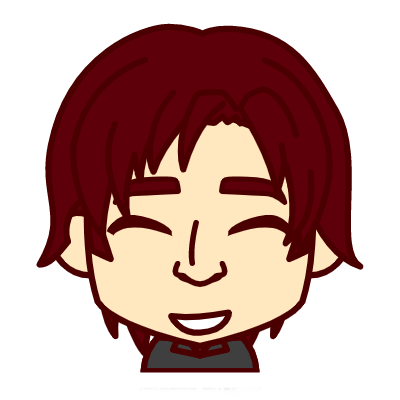
…
!!

いやぁ、あたかも自分で考えたかのように錯覚しちゃダメっていう良き例ですね!
アナイグマのひとこと
情報が増えたことで供給される情報のクオリティに対する期待値も上がり、消費者の目が肥えてきたというのが現状ではないでしょうか。例えば「スーパーで新商品買って食べたら美味しくなかった」というケースだと、昔なら「美味しくなかったなー仕方ないか。もう買わない。」だったところを、今だと「口コミも見て美味しいと思ってたのに!もう買わないどころか拡散する!」と極端に言うとこんな感じではないでしょうか。意見を言える場(SNS)が増えたこと、それにより一般消費者が評論サイドに立てるようになった。そしてこうした意見が乱立することで単純な括りではなく、多様化したユーザーのセグメントやコミュニティといった単位が増えてきた。マーケティングの世界でもオートメーションが進み、配信も機械に任せるようになった。生成AIが出てきて、より考えることが減った。でも実際に商品・サービスを購入・利用するのは人間です。選ぶ側の消費者にもAIによるサジェストや依存は発生していても、自分の全てを理解し提案してくれるAIはまだありません。人間の心理は推測だけではカバーできません。事実は小説より奇なり。その奇を拡大推計してストーリーを組み立てられるのも人間です。AIの精度が上がっても、生身の人間の発想には追い付かないと思っています。そう私は信じてます。